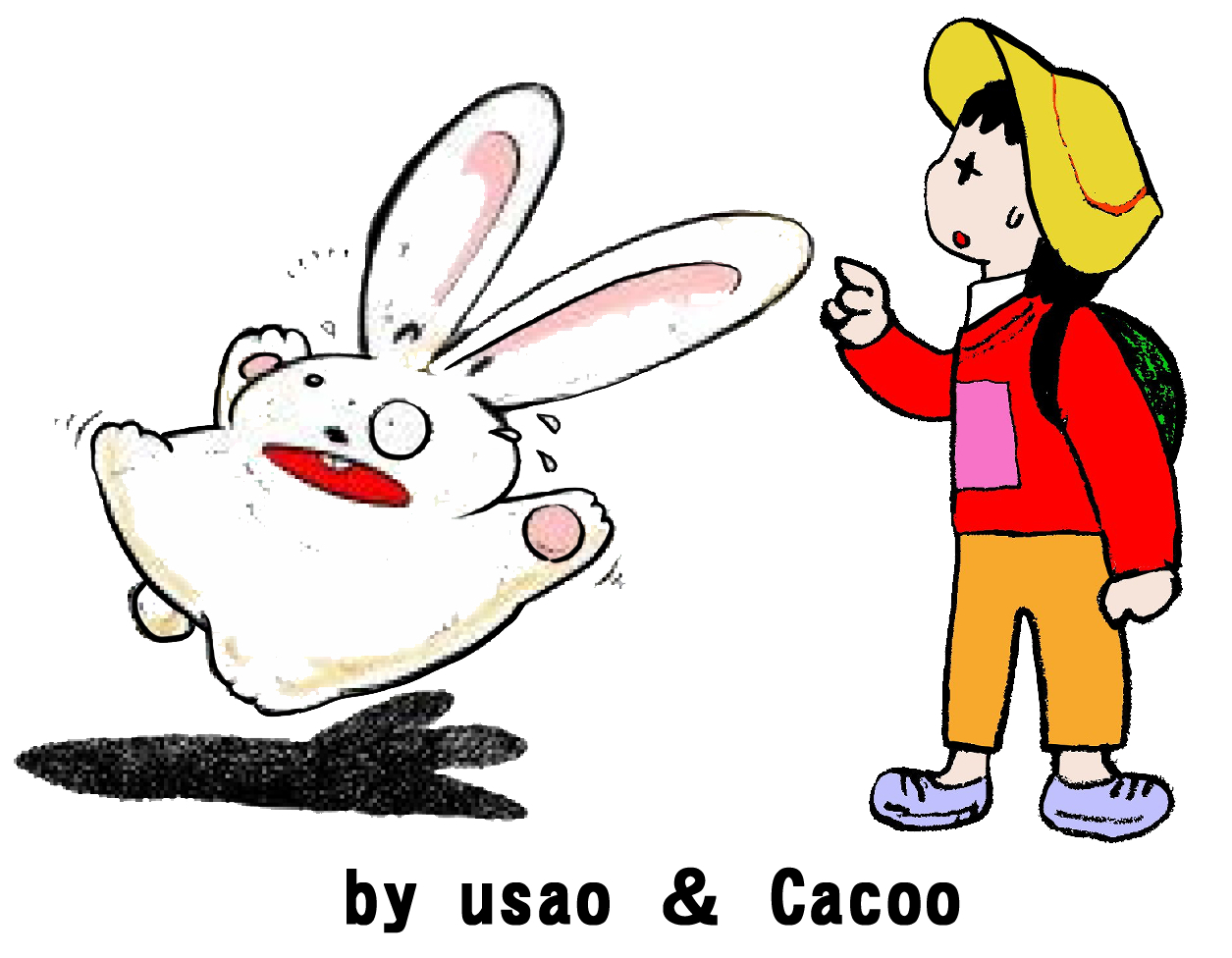
新橋から少し戻って歩いてみる 第一回
うさお&Cacco
ああ、煉瓦高架橋がコンクリートになってしまう
JRの新橋駅は、明治40年に完成した煉瓦アーチ高架橋をそのまま用いています。
この高架橋の下は、店舗や駅施設として用いられていますが、何しろ、アーチ構造ですので壁や天井高が広く、高くは採れません。しかも高架橋の縦断方向(線路が敷設してある向き)は、小さなアーチが連なっている構造で、空間がいくつにも分断されてしまいます。
とはいえ、この高架橋のアーチで囲まれた空間は、店舗としては程よい大きさで、飲食店とか、倉庫、駐車場に利用されています。
明治40年頃までの東京の鉄道は、東北線は上野駅まで、東海道線は新橋まで、中央線は萬世橋駅までが開通していましたが、現在の東京駅のあたりは鉄道が何も無かった空白の地域だったようです。
確かに中央停車場駅(現在の東京駅)が出来るのが、大正3年のことですから、そこまでの間に、新橋―東京、東京ー万世橋間が煉瓦高架橋で繋がれたことになります。新橋ー永楽町間の煉瓦高架橋を、新永間市街線と呼びます。永楽町名は昭和4年に廃止されますが、今の千代田区大手町、丸の内のあたりで東京駅の八重洲口あたりでしょうか?
※東京鉄道遺産 小野田滋著より

新橋駅煉瓦高架橋 断面模式図 (2015年7月4日)
図にありますように、西側は煉瓦高架橋が残っており見ることが出来ますが、東側は東海道線のコンクリートの高架橋があるため、煉瓦アーチは見ることが出来ません。東京を過ぎたあたりでようやく、東海道線の高架橋が無いため、東側でも煉瓦アーチを見ることが出来ます。
で、この煉瓦高架橋の新橋駅近辺が、耐震補強のため部分解体され、鉄骨とコンクリートで補強されることになりました。煉瓦アーチが無くなっちゃう。
わあ、すぐにでも見に行かなくちゃあ。caccoとGURIKO隊長に連絡をします。GURIKO隊長は旦那様のお手伝いで参加できません。すぐにも取り壊されてしまうかもしれませんので、とりあえずcaccoとうさおが、先遣隊で見に行くことにしました。2015年7月の頃です。
新橋駅に着きました。新橋駅の烏森口の方に降りてみます。

新橋駅烏森出口 大きなステンドグラスがお出迎え 2015年7月4日
駅構内に何やら遺構が残っています。ホーム階段を支えてきた柱の一部がここに残されています。明治41年に造られ、平成14年に解体されたものです。

新橋駅 黒い鉄柱が建っています 2015年7月4日
烏森駅開業時 「柱」の由来 2015年7月4日
明治42年烏森駅開業時「柱」の由来
明治5年(1872年)、新橋・横浜間に日本で最初の鉄道が開業いたしました。
当時の新橋駅は、現在の東新橋付近に設置され、「新橋停車場」として親しまれましたが、大正3年(1914年)、東京駅開業により42年間の幕を閉じました。なお、それまで使用されてきた、同駅は「汐留駅」と改称し昭和61年に役割を終えました。
現在の駅は明治42年(1909年)12月、わが国初の高架駅(烏森駅)として誕生。同時に山手線電化工事が完成し、烏森~品川~新宿~池袋~田端~上野間で電車運転を開始いたしました。
そして、大正3年(1914年)12月、東京駅開業に合わせて新橋駅と改称し現在に至っております。
平成14年(2002年)、3、4番線ホームエスカレータ新設に伴う階段解体工事のため、93年間ホーム階段を支えてきた「明治41年製造」の柱を取り外し現在地にて保存することになりました。
平成14年7月 新橋駅長
もともと、烏森駅と称された駅で、本来の新橋停車場は、ゆりかもめと昭和通りに囲まれたところに、旧新橋停車場跡として残されています。今は鉄道歴史展示室となって居ます。

旧新橋停車場 現鉄道歴史展示室 2019年3月15日
新橋駅から汐留に少し戻ってみる
新橋駅から浜松町駅の方に少し戻ってみます。日比谷神社のある交差点に辿り着きますが、この先の浜松町方は低盛土になっていますので、この交差点から新橋寄りが、残存する煉瓦高架橋の始まりと言えます。浜松町方の煉瓦構造物ば、新銭座ガードの橋台などに面影を残しています。

新橋駅から汐留方面 赤線が辿ったところ 2015年7月4日 googlemapより
市街地における鉄道高架橋を設計したのは、ベルリン市街線を設計したフランツ・バルツァーで、高架橋は概ね外堀に沿って造られています。用地の確保が容易だったのかも知れません。

新橋駅烏森口 2015年7月4日
新橋駅(烏森口)を出ると烏森通りと高架橋が交差しており、浜松町寄りにあるのが、日蔭町橋高架橋です。
この更に先に浜松町方に第2源助町橋高架橋があります。
新橋駅から日比谷神社方面へ 日蔭町橋高架橋 2015年7月4日

日蔭町橋高架橋の耐震工事中 煉瓦が無くなる 2015年7月4日
日蔭町橋高架橋 電架柱の鉄骨が高架橋の外にある 2015年7月4日
この高架橋とガード下の道路が交差するところが、芝口橋架道橋と浜松町方に第2源助町橋高架橋があります。新橋方が日蔭町橋高架橋なので大変入り組んでいます。それにしても終戦後の雰囲気を色濃く残している地域です。
日蔭町橋高架橋から第2源助町橋高架橋へ 2015年7月4日
その間に芝口橋架道橋 三叉路だったのか 2015年7月4日
日蔭町橋高架橋と右の芝口橋架道橋 通路は新橋駅南口に通じている 2015年7月4日

第2源助町橋高架橋 南に通じる通路もある 2015年7月4日
第2源助町橋高架橋 橋側歩道の支方を記憶しておいてね 2015年7月4日

第2源助町橋高架橋 おじちゃんいい味出してる 2015年7月4日
第2源助町橋高架橋と環二通り交差点 鉄橋は源助橋架道橋 2015年7月4日
この煉瓦高架橋は、先も記したようにドイツ人のバルツァーの企画・設計ですが。、『東京駅誕生 お雇い外国人バルツァーの論文発見』鹿島出版会に詳しく載っています。バルツァーの論文の抜き刷りは、鉄道総合技術研究所の図書館に保存されているそうです。

フランツ・バルツアーの高架橋の図面 2015年7月4日
お目当ての新橋駅の煉瓦高架橋の改修
新橋駅に戻って、お目当ての耐震改修箇所を見てみます。

新橋駅烏森口に戻ってきました 2015年7月4日
新橋駅 烏森通り交差点 2015年7月4日
ここは、工事終了後、煉瓦造からコンクリート、鉄骨造に変わり、全く違う構造になるところです。でも、工事用の柵があり全く見えません。ありゃりゃ。

新橋駅 工事現場 2015年7月4日

新橋駅 工事現場 2015年7月4日

新橋駅 工事現場 これだけじゃ何もわからないなあ 2015年7月4日
面白いので、ニュー新橋ビルに入ってみる
新橋駅のあたりを少し散策してみます。汽車(SL)広場で記者に取材されたいな。
新橋汽車広場 よくテレビで取材している処 2015年7月4日

心身障碍者に愛の手を 2015年7月4日
乙女と盲導犬の像 2015年7月4日
「乙女と盲導犬の像」
街は
こんなにも明るいのに
どこかに翳りのある
心のささくれ
あなた
語らずにぬくもりと
求められずにぬくもりと
あの街に
この街に
川内康範
川内康範は月光仮面の原作者で、「誰よりも君を愛す」、「君こそわが命」、「骨まで愛して」、「恍惚のブルース」、「花と蝶」、「伊勢佐木町ブルース」、「おふくろさん」などの作詞も手がけました。
ニュー新橋ビルの入り口で、大判駒の将棋大会が行われていました。
昔、昔に、渋谷の宮下公園には、プロの将棋指し(真剣師と呼ばれているようですが)が居て、お金を賭けていました。アセチレンランプの下で、将棋の好きなお父さんたちが目の色を変えて、指していましたよ。素人目には詰みそうで詰まない盤面の勝負だったようです。詐欺みたいなものです。1手50円~100円で安いのですが、相手が指す手も、手戻りもカウントされ、さらに解説をされて、盤を動かすと、その手もカウントされますの、結構大きな額になり、お父さんは青ざめることになります。
今回の将棋大会は賭け将棋ではありません。
ニュー新橋ビル 2015年7月4日

新橋大判将棋大会 受付のお兄ちゃんはつまんなさそう 2015年7月4日

大判将棋だっ!駒が大きい 2015年7月4日
結構大人気 腕に覚えのある人が見ている 2015年7月4日
お腹も空いてきたので、地下の飲食店街に行ってみました。ここは昭和の香りをほのかに残したお店が並んでいます。

ニュー新橋ビル 地下街 2015年7月4日
一軒を選んではいってみました。若い女の子二人で店を切り盛りしています。先に陣取っていたおじさんたちとにこやかにやり取りしていますが、あれ、一人は中国人ですね。もう一人はベトナムあたりの人じゃないかしら。写真は撮れなかったけど。

ニュー新橋ビル 和食店 じゅらく 2015年7月4日
でも出てきた料理は、和風です。う~ん、突出しはちょいと、中華が入っているけど、辛くて旨いぞ。

ニュー新橋ビル 天婦羅定食かな 2015年7月4日
今回はここまで。次回は有楽町まで歩きます。